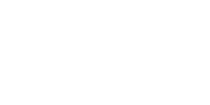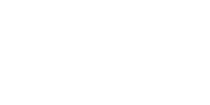「常識を疑うことで」
工業用ハイスピードカメラはセンサーひとつの単板式が一般的。これに対し画質要求の高い放送用カメラはRGBそれぞれ異なるセンサーで画像を記録する、いわゆる三板センサー方式だ。これだけでも両者の設計思想は大きく異なる。加えて放送用カメラならではのユーザーインターフェースなど、ナックにとって未知なことだらけであった。構造上配置に無理のない箇所にコネクターをもってきても、「いや、このケーブルはここから出ないと現場での使用が難しい」「このスイッチはここにないと」と放送の現場から細かい仕様上の要望が出てくる。それらひとつ一つに対応しながら、Hi-Motion初代機の開発は進められ、2004年秋には特集番組で試作運用。年末には「毎秒300コマのハイビジョン対応ハイスピードカメラを開発」と報道発表がなされ、翌2005年の春には放送業界の世界最大の見本市であるNAB(National Association of Broadcasters)で講演形式による製品発表が行なわれた。
ただ公式に製品発表されたものの、開発の現場では“ある問題”との格闘がつづいていた。それはノイズである。非接触アイマークレコーダーの開発を終え、後藤がHi-Motionのプロジェクトに参加したのは2004年の10月。まさに開発が最終段階を迎え「ノイズをいかに除去するか」が最後の大きな課題となっていた頃だ。「1/300秒という最速領域での使用で、被写体の明るさによって画面を横切るノイズが発生してしまう。これを何とかして除去するのが、私の最初のミッションでした」と後藤は当時を振り返る。

機能的なHi-MotionIIのスイッチ。 当時のナックにとって、放送用カメラはすべてが手探りでの開発だった。

手前から初代Hi-Motion、Hi-MotionII試作機、現行Hi-MotionII。
様々な進化を遂げているのがわかる。
開発は最終局面。筐体はもちろんだが、内部の回路設計も大きな変更はできない。後藤はすでに形になっているカメラの内部モジュールを手に、センサーのパラメーター設定など、細かな見直しを何度も繰り返し改善のヒントを探る。しかしなかなかその糸口が見つからない。そんなある日、工業用ハイスピードカメラ開発でセンサー技術に豊富なノウハウを持つ上司から「思い切ってパラメーターの設定値を大きく変動させてみてはどうか」という助言を受けた。そこで、これまでセンサーメーカーの仕様書に従って設定していたパラメーター数値を見直し、新たな視点で検討することにした。
センサーは光を受け、それを読み出し電気信号に変えて記録媒体へと送る。その極めて短い1/100万秒ほどの間に処理が行われているあるパラメーターに注目した。「見つけたパラメーターはほんの一瞬を制御する値でした。ところが助言を受けてそれを調べてみると、毎秒300コマという高速撮影、さらには放送用の信号規格に合わせ信号を増幅した場合、その処理が原因となって横引きノイズを発生させていることが分かった」(後藤)
後藤はセンサーの制御パルスの設定値を変更する。何度も試行錯誤を繰り返しノイズが発生せず、かつ記録速度がもっとも速いパラメーターを探っていった。しかし、いくら条件を変えてもノイズを取りきることができない。そこで後藤はある意味“禁じ手”のような手法を用いる。
「センサーのドライブ速度を仕様書に示されている最大値まで上げ、さらに制御パルスの形状やタイミングを標準的な設定とは全く違った内容に変更する検討を行いました」後藤は簡単に話すが、これはあくまでもHi-Motionの仕様に特化した制御系の設計であり、通常のセンサー駆動の常識とは異なる物であった。そしてついにその独特の制御系設計によって、ノイズが発生しない毎秒300コマの映像を出力することに成功したのである。
冒頭にあるように2006年の天皇杯サッカーの中継で使用されると、その映像は高い評価を獲得。同じ年のサッカーワールドカップ・ドイツ大会で使用されたことをきっかけに、ウィンブルドンテニス、さらには2008年の北京オリンピックにも採用される。それまで放送用カメラをつくったことのない、いわば名もなき会社の製品が、世界最高峰のスポーツ中継で採用されたのだ。
2011年にはアメリカテレビ芸術アカデミーにその功績が評価され、技術・工学エミー賞を授与される。それは前述の放送関係者の言葉にあるように「ある日突然、何かものすごいカメラをつくった」という驚き、いやそれ以上のインパクトを放送業界にもたらした。

初代Hi-Motionは、サッカーワールドカップ、ウィンブルドンテニス、北京オリンピック、広州アジア大会、MLB、NFLなど、様々なスポーツイベントで活躍した。