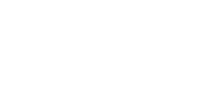映画の作法、ドラマの作法

| ── | 英夫さんの最近のお仕事のひとつに、TBSのドラマ『S -最後の警官-』があります。映画界のトップキャメラマンがドラマのキャメラマンとして参加されるということで、業界ではかなり話題になりました。こうした仕事に挑むってことは、やはり英夫さんは挑戦者なんだなって思うんです。 |
|---|---|
| 山本 | 最初、TBSの知り合いのプロデューサーから呼ばれて話を聞いた時は、映画の話だったんです。ドラマを受けた映画化の計画が最初からありましたから。原作のマンガも読んで、けっこう面白いなと思いましたけれど、少し先の話だったんですぐにどうこうという感じではないと僕は思ってたんです。ところがプロデューサーから「実はその前にドラマでやるんですが、それも撮ってもらえませんか」っていきなり切り出してきまして(笑)。「僕は映画のやり方しか分かりませんよ」「マルチキャメラなんてできないし、やりたくないですよ」と、実は最初は及び腰だったんです。それでも、「いや山本さんのやりたい方法でやってもらって構いませんから」って言ってきまして。 |
| ── | おそらくドラマと映画で、画の世界観をつなげたかったんでしょうね。 |
| 山本 | どうなんでしょうね。とりあえずその場では即答せずに「少し考えさせてください」ってことにしたのですが、原作を読み、キャスティングとかの情報を聞いているうちに、何か刺激が欲しかったのかなあ(笑)。時々あるんですが、難しいと分かっていることにあえて飛び込んじゃおうか、って気持ちが頭をもたげてきたんです。そんなに深く考えたわけじゃなくて、むしろ「やっちまうか」っていう感じで。ただ受けてから思いましたよ、「撮影半年か、長いなー」とかね(笑)。 |
| ── | 撮影に関しては英夫さんの要望を叶えてくれたそうですね。 |
| 山本 | ええ。キャメラはALEXAを使うとか、映画と同じスタンスで撮影できるようにして欲しいと希望を伝え、心の中では「半分も叶えばいいかな」って思っていたのが、ほぼ対応してもらえた。若いプロデューサーだけど相当頑張ってくれました。 |
| ── | そうは言っても、やはり映画とテレビドラマの制作環境は違いますよね。 |
|---|---|
| 山本 | もちろんです。たとえばカット割ひとつにしてもテレビドラマはコマーシャルも入るし、チャンネルを変えられないよう視聴者を飽きさせない工夫など、独自のテンポがあります。説明調になるカットでもドラマの作法では必要なものもある。予想はしていたけれど、最初はその違いに戸惑いました。慣れるまで1~2話分かかったかな。 ただ最終的にはそうしたテレビドラマの常識よりも、むしろ自分がこれまで培ってきた映画のスタイルでの撮影になっていったかな。もちろんテレビドラマとして必要なカットは撮るけれど、テレビのやり方に自分があわせるのでは、自分が撮る意味はないわけですから。自分が持つ映画のスタイルとテレビドラマの手法が上手く融合すれば良い、と考えるようになっていきました。 |
| ── | テレビドラマと言うと1話が約45分で全10話など、映画に比べて作品の絶対的な時間が長い。そうなると撮影の効率とか、時間の制約が相当に厳しいのだろうと推測しますが。 |
| 山本 | 効率を考えながらも、自分の撮りたい画、伝えたい画とのバランスをどう取るかです。ある意味効率を優先して流れ作業になるとしたら、むしろそれは楽なことなんですよ。言われた通りにただ撮っていけばいいんだから。でもそれだとしたら、僕である必要はないわけです。 時間がない中でも、脚本を読んで自分の世界観をつくって撮影に挑む。体力的なきつさよりも、それがきちんとできているか否かでの、精神的な部分が一番辛かったかな、今回のドラマを経験して。時間的なことなどから、どうしても妥協しなくちゃいけない部分もありましたから。 |
| ── | さて、特にテレビの世界での技術的な話題と言えば4Kです。話題が先行している感もありますが、映画キャメラマンの立場から4Kをどう見ていますか。 |
|---|---|
| 山本 | ハードが先走っていて、その受け手である我々人間にとってどうか、と言うのが追いついていない、ないがしろにされている印象を受けますね。 2020年に東京オリンピックがありますが、4Kはそれがひとつのターゲットでしょうね。おそらくスポーツ中継の世界などには馴染むだろうし、一瞬をより高精細に切り取ることで、スポーツの持っているダイナミック部分や肉眼では捉えきれないアスリートの高度なテクニックなどを伝えることができると思います。 ただ、その恩恵を映画がそのまま受け取れるかと言ったら違うでしょう。経済的な面では上映システムへの投資を考えただけでも、額が莫大なだけに、そうガラッと一気に進むとは思えません。映画で言うとフィルムとデジタルの話にも共通しますが、仮に高精細で撮ったとしても、今の映画づくりを見て分かるように、つくり手側は画を汚す。言い方を変えると、きれいに写り過ぎていることを嫌ってさまざまな処理を行っています。言ってしまえば、フィルムの感じにしているわけですよ。解像度などだけでは測れない心地良さとか、いわゆる味ってものがあるからです。 4Kの場合にも「きれいすぎることの弊害」が、映画というエンタテインメントにおいてはあるのではないかと思いますね。もちろん慣れてきて、それを活かす場面というのも当然出てくるでしょうけれど。すぐにそうなるとは考えにくいですね。 |