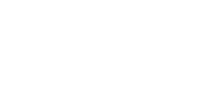キャメラマンにとっての至福の瞬間

| ── | 最後のパートは当社の社員からの質問にランダムに答えて頂きたいと思います。社員には映画好きもかなり多いので、どうぞよろしくお願いします。 |
|---|---|
| 山本 | お手柔らかにお願いしますよ(笑)。 |
| ── | 「山本さんがキャメラマンとして影響を受けた映画、好きなシーンなどはありますか?」 |
| 山本 | 言って見れば自分の好きな映画っていうことですよね。世界観が好きな映画っていっぱいありますけれど、あえて挙げるならタルコフスキー監督の作品はすごく好きですね。なかなか手に入らないDVDがあって、しかも高いんですよ。1枚2万円とかする。それ一生懸命集めました。あとはジム・ジャームッシュ監督の作品も好きかな。キャメラマンも含めて。 |
| ── | 「映画を観る時、やはりキャメラマン目線になりますか?」 |
| 山本 | 主には純粋に作品を観ることが多くて、キャメラマンのことは見終わったあとに考えることが多いかな。ただ、たとえばロビー・ミューラーってキャメラマンが撮った作品なんかだと、観ている最中から知らない間にキャメラマン目線になるってことがあります。おそらく何か感覚的に符合するものがあるのか、もしくは自分には無い世界観を持っているからなのか、ちょっとその理由はきちんと分からないけれど。 |
| ── | 「山本キャメラマンが影響を受けたキャメラマンは誰ですか?」 |
| 山本 | これは助手時代に付いた撮影所の先輩キャメラマンたちですね。特に撮影助手が影響を受けるのはフォーカスマン時代です。常にキャメラマンのそばに居るし、フォーカスを送っているからキャメラマンがどういう意図で、どういう画を撮っているかが分かる。逆に理解していないとフォーカスなんて送れませんから。未だにそうやって助手として付いていた先輩方のクセが自分に乗り移っているなと思うことも多いですよ。 |
| ── | 「もしキャメラマンになっていなかったら、何をやっていたと思いますか?」 |
|---|---|
| 山本 | SATでしょうね(笑)。 |
| ── | それさっきのドラマの話じゃないです?(笑)。 |
| 山本 | それは冗談として、ちょっと他の職業ってのは想像付かないですね。 |
| ── | キャメラマンになるべくして生まれてきたと。 |
| 山本 | そんなカッコいいものじゃないですよ(笑)。 |
| ── | 「画づくりへのこだわりを教えてください」 |
| 山本 | これよく誤解されるんですが、映画キャメラマンにとって、最初に画づくりがあるわけではないんですよ。むしろ最初に画はない。 |
| ── | 意外な答えですね。 |
| 山本 | ひとつひとつのシーンには、それぞれ意味がありテーマがあります。何でそのカットを撮るのか、どういう演出意図を伝えなくてはいけないのかをキャメラマンは考えるわけです。まずは台本を徹底的に読み込んでいく。すると自分なりの一本の映画が頭の中にできあがってきます。それは具体的な映像がつながったというより、漠然としたイメージのようなもの。もちろんそれが監督のイメージしたものと違うこともありますし、仕事を進めていく中で頭の中のイメージはどんどん変わっていきます。 現場がスタートし、監督がカット割をして、役者が来て実際に演じる。それからです、画を考えるっていうのは。目の前の芝居を伝えるにはどういうサイズで、どういう距離感で、だからどういうレンズを選択すべきかということを考え、判断する。構図が先にあるわけではないんですね。僕はそう言う意味では“カッコいい画”って言うことにこだわりはなくて、むしろ“映画全体の中でのワンシーンが持つ意味”ってものを考えています。時々現場で「画を決めて欲しい」と、先に言われることがあるけれど、僕はそれは映画として違うんでは、と思いますね。 |
| ── | キャメラマンとして、カッコいい画をつくるかには相当なこだわりがあるのだろう、と素人は思いますが違うんですね。 |
| 山本 | 画の切り取り方がうまい、構図のセンスがあるという人はたくさんいます。プロでなくてアマチュアの人でも。そういう独特のセンスを持っている人はいると思います。もちろんそれを否定はしませんけれど、映画キャメラマンとしての僕が重きを置いているのは、そこではないってことですね。 |


| ── | 「自分の意図に反する撮影の注文が監督からきたら、どうしますか?」 |
|---|---|
| 山本 | よくこういうこと起きますけれど。僕はまずその意図を徹底的に探ることにします。自分はこんなカットいらないし、そんな撮り方はしたくない、って場合、何で監督はそれを要求してくるんだろうって。で、その考えの奥底にあるものを引き出す。そうすると見えてくるんですよ、彼の意図ってものが。それが納得できるものなら、そのまま撮ることもあるし、逆に意図が理解できたからこそ、逆にこちらからプランを提示することもできますよね。 |
| ── | 「今、撮ってみたい映画は?」 |
| 山本 | 純文学かな。昔の松竹作品のようなものを撮りたいというわけではなくて、あくまで今という時代に即した文学作品的な映画を撮ってみたいですね。今、日本映画の主流はマンガの実写化などで、それは興業的なこと考えると仕方ないのかもしれませんが、意欲のある監督のオリジナル作品なども出てこないと映画界のためにはね。 実はいろんな監督がアイデアを温めているし、動いているんです。ただいかんせん、そうした企画は通りづらい。マンガ、ドラマなどの映画化という方が投資サイドとしては、一定の担保があるというか、イメージしやすいですからね。 |

| ── | 「フィルムとデジタルを比べた時、フィルムの良さとは何でしょう?」 |
|---|---|
| 山本 | 繰り返しになるけれど、一番大きいのは技術面じゃなくて、その制作の過程、映画づくりに臨むアプローチの違い、そこに何かがあるように思うんです。 ひとつは先ほども話したモニタリングできるかどうかの違い。モニタリングは本当に便利だし、失敗も軽減できるし、確実に撮った画をその場で把握できるから、効率やコストを考えたら良いことしかない。けれど便利さが故に薄れてしまうものもある。そのひとつがイメージする力、想像力だと思うんです。 フィルムの時にはモニタリングがないから、どのようにフィルムに定着されるかということを常に意識し、その像を脳の中に描いて撮影します。もちろん露出メーターで詳細に光量を計測して、それに基づいてキャメラの露出を決める。ただしメーターの数値はあくまで光の強さを示すだけ。つまりその数値をもとに、キャメラの露出を決めるってことは、レンズを通した光が、フィルム上でどんな像となって定着されるか、濃度とか色とか含めて、いろんなことを頭の中でイメージしながら撮るということ。相当に研ぎすまされた感性がそこには必要だっていうことです。それはキャメラだけでなく、映画づくりのあらゆる過程に当てはまる。そんな緊張感や高いレベルでの感性のぶつかり合いが、一本の映画に出てくる。 たとえばかつての大映映画とか、名作と呼ばれる作品がたくさんありますが、あの頃って映画量産時代ですから、スケジュールなどを考えれば、今以上に厳しかったはずです。それがなぜ未だに名作と評価されるのかって言えば、それはつくり手の意識の高さなのではないかと思うんです。 |

| ── | では次に弊社がカメラメーカーと言うこともあり、是非お聞きしたい質問を。 |
|---|---|
| 山本 | ハイスピードキャメラって、一般的には速く動く被写体を撮って、その動きをスローで見せる。カーチェイスとか、クラッシュ、爆破のシーンなどが効果的だと思われています。もちろんそうした使い方もしますが、僕はあえて普通のシーン、たとえば役者のアップを撮って、一瞬の表情の変化で内面の意識の変化が見えるというような場面に使いますね。それまで普通の表情だったのが、相手のある言葉に反応して、微妙に険しい顔になる。その変化をハイスピードで撮る。台詞はないけれど、本当にわずかな眉や口角の動きで、人間の内面の変化が見て取れる、実はこれこそハイスピードならではの画じゃないかって。 |
| ── | アシスタントの方などは、少し驚くんじゃありませんか。「ここでハイスピード?」って。 |
| 山本 | そうですね。不思議そうな顔して「ハイモーションですか?」って聞き返されることありますよ。そんな時は「そうだよ、ガタガタ言ってないで早くもってこい」って怒鳴ります(笑)。 |
| ── | 「山本キャメラマンがキャメラの性能面でもっとも重視することは何ですか?」 |
| 山本 | まずは安定性です。映画撮影に使うわけですから、現場で突然動かないなんてのは困る。何を置いても安定性が最重要です。それと先ほども言ったファインダー。これはプロキャメラマンとしてメーカーには早急に研究して欲しい。センサーが心臓部だとしたら、ファインダーは第2の心臓ですよキャメラマンにとって。 全体的に言うと、もっと機材はシンプルで良いんじゃないかとも思います。ここにあるALEXAは割合シンプルな方だけど、僕からすると余計な機能が多すぎるような気がする。もちろん便利さや高機能化を頭ごなしに否定するつもりはありません。けれども使い手側の人間の意識とか、想像力の範囲とかけ離れすぎるというのは、特に映画づくりという面で「どうなのだろうか」と疑問を覚えるんです。キャメラ任せで素晴らしい画が撮れちゃった、それは結果として良いのかもしれないけれど、撮るつもりで撮った画と、撮れちゃった画っていうのは違いますから、特にプロの世界は。 技術の進歩が生活に寄与することは大きいし、キャメラで言えば産業分野とか医療などの領域では高機能化、高精度化が意味を持つでしょう。見えなかったもの、分からなかった現象が、キャメラの進化で捉えられるようになることで、飛躍的な技術進化を生み出すことがあるはずですから。 ただ一方で映画に限って言うと、むしろ撮る側、つくり手側である人間がコントロールできる、人に寄り添うキャメラであって欲しい。その意味ではあまりに人智を超えるべきではないのではと思いますね。 |
| ── | たとえばインターフェースの部分などを設計するにしても、今のお話は肝に銘じなくてはいけない所ですね。技術はもちろん進化しなくてはならないけれど、それはやはり使い手側、私たちの仕事で言えばキャメラマンの方々に寄り添ったモノでなくてはいけないわけですからね。 |
|---|---|
| 山本 | まず学生時代から知っている盟友でもある三池崇史。元をたどれば八尾の不良ですけれど(笑)。職業映画監督としては、今、日本でナンバーワンでしょうね。古くから知っているけれど、いつもシャープだし、関係が古いからと言って“なあなあ”にならない、させない、彼のプロ意識はすごいと思います。 それと井筒和幸さんとも何本もご一緒してますが、あの人もすごいですね。ご存知の通り、一見クセのある人ですけれど(笑)、実はその発言を聞くと、自分の立ち位置がいつもしっかりしていて、ぶれないし、理にかなっている。映画づくりに関していうと、自分の中に確かな一本の筋、自分なりのたしかなロジックを持っている希有な監督のひとりだと思います。 僕がまだ若い頃、ある乱闘シーンの撮影でちょっと変わった、カッコいい画づくりをしようとしたことがあって、若いときはやりたがるんですよ、自分らしさを映画に残したいから。そうしたら井筒さんが「わかるんやけど、ちょっとカッコ良すぎるんや」って言うわけです。最初はその意味が分からない、こっちも若いから「カッコいいのになんでダメなんだ」って。でも一本の映画全体を考えると、たしかに井筒さんが言うように、そこにカッコいい画は必要ないことが分かってくる。一見大雑把なように見えるけれど、本当に繊細で、地にしっかり足をしっかりつけて映画づくりをする人ですね。 それと思い出深いと言えば(北野)武さんの「HANABI」ですね。武さんって役者に演技を過度に要求しないことで知られていますけれど。キャメラマンにも細かい指示がないんです。「山本さん、こっちから撮って」って言うくらい。たまに「もう少し寄ろうか」とかはありましたけどね。凝った画づくりとは真逆で、逆にシンプルそのもの。あの撮影では多分レンズ2~3種類くらいしか使っていない。ある種ものすごく禁欲的な撮影でしたね。 そんな中で、武さんを撮るシーンがあって、それは引きの画の中に、武さんがポツンと立ってキャメラ目線というすごくシンプルなシーン。でもファインダー覗いた時、武さんの存在感と画の力強さにしびれるような想いを感じたのを今でも覚えています。本当にただ立っているだけ。それでもいつまでも見ていられる。もうカットかけないでくれっていう感じ。 そんなカットを最初に見られる。それはキャメラマンの特権だし、この仕事やっていてよかったって思える瞬間ですよ。あれは助手とかではわからない。キャメラマンだけが知る世界です。だから僕は「もう辞めたい」みたいなこと漏らす助手がいると、よく言うんですよ。「お前まだ何にも見てないんだぞ。ここから見る世界は全然違うんだぞ。見ないで辞めちゃうのか」って。 |
| ── | キャメラマンは映画の最初の観客とも言われますよね。 |
| 山本 | そう。ただ最近では皆モニターで見ちゃっている。それも気に入らない所なのかな(笑)。 |