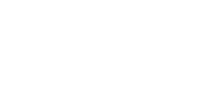ドラマづくりの
醍醐味を味わった『カルテット』

| ── | 人間の持つ多面性。脚本家が生み出すオリジナル作品の世界観。つくり手の思い。俳優たちが織り成す現場の化学反応。今までお聞きしたことが、ドラマ『カルテット』にはつまっているような気がします。 |
|---|---|
| 土井 | 『カルテット』の企画は3年くらい前から始めていて、佐野亜裕美さんというプロデューサーと一緒に立ち上げた企画です。僕らの強い思いは坂元裕二さんの脚本でオリジナルドラマをやりたいということ。そして主演の4人、松たか子さん、満島ひかりさん、高橋一生さん、松田龍平さんが坂元さんの描くストーリーの中でどんな化学反応を起こすのか、それを見てみたかった。つくり手としての思い、その芯が何であるかといわれれば、出発点にあったこのことに尽きるかもしれません。 |
| ── | 視聴者としては良い意味で最後まで振り回されたドラマでした(笑)。 |
| 土井 | 最後の着地点っていうのが実は僕らも確実には見えていなくて、ストーリーにしても松さん演じる真紀さんのご主人が現れて、みたいなとこまでは何となく見えていましたが、まさか第8話で真紀さんが真紀さんじゃないという事実を、上がってきた台本を読んではじめて僕らも知った。それは驚きましたね。 |
| ── | 視聴者の驚きは、私を含めその比ではありませんでした(笑)。ただ一方で着地点が明確に見えない不安みたいなものはなかったのでしょうか。 |
| 土井 | 最終的にハッピーエンドになるの?バッドエンドなの?とか、この人は良い人か悪い人かとか、最近はすごく分かりやすい色分けが求められる中、この『カルテット』はラブストーリーなのかサスペンスなのか、ジャンルもはっきり分からない、語るのが難しいドラマでした。でも坂元さんが人間を描きたいという部分にブレはなくて、そこを僕らは信じられた。だからおのずと不安はありませんでした。 |
| ── | 「どこに行くのだろう?」って思いながらつくる現場の高揚感。連ドラならではの醍醐味を味わったという感じですか? |
|---|---|
| 土井 | そうかもしれません。毎回面白い台本が上がってきて、それを演じている役者さんを撮る。その喜び、楽しさが毎回ありました。『カルテット』では1シーンが10ページ以上あるような会話シーンとかあって、それを初めて現場で役者さんが演じる。その生まれたてのシーンを一番最初につくり手である僕らが見る、その喜び、ワクワク、もちろん緊張感も含めて「あぁ、ドラマつくるって面白いな」と改めて僕は思ったし、スタッフもそう感じてもらえたんじゃないかなと信じています。 |
| ── | では、この辺りで画作りに関してお伺いします。作品の世界観を表現する上で画の質感は重要な要素だと思うのですが、今回の作品では何かこだわった点などありますか? |
| 土井 | 『カルテット』では冬の軽井沢、別荘が舞台で、その質感、空気感を表現するということが一つのテーマ。あまりファンタジーになりすぎず、かつ独特の手触り感を表現したい。そのアプローチのひとつがデジタルシネマカメラの採用ということでした。印象的だったのは冬の軽井沢の中にあるグリーンの発色が、モニターで見たとき肉眼以上にきれいだったことでしょうか。 |
| ── | やはり土井さんは画の世界観、空気感みたいなものにこだわるタイプですか? |
| 土井 | ディレクターにはいろんなタイプがいて、画作りから何から、細部まで自分の世界で染め抜きたいと考える人、一方で技術には興味があまりなくて、役者の演技に集中する人など。僕はどうでしょう、自分では真ん中くらいかなと思っていて、こだわりはなくはない、けれど自分で全部決めるのではなく、スタッフの提案を受ける余白は残しておきたい、という感じでしょうか。ディレクターなりの世界観があるにしても、映像や美術、それぞれのエキスパートの持っているイメージを持ち寄り、意見を戦わせる。そのことで僕の中にはないものが見えてくるし、自分の世界をそれによって広げてもらいたいと思っているんですね。自分の思いつく範囲、イメージできる範囲ってすごく限られていて、それは長くやっていればいるほど分かってくる。むしろ自分の中にはない他からの発想を受けて、世界がどう広がっていくかっていうことの方が僕はずっと面白い。結果、その経験によって次に僕がイメージできる範囲が広がっていくわけですから。 |


| ── | 画の世界観でいえば、かつてドラマはビデオ、映画はフィルム、という感じだったのが、最近ではデジタルシネマカメラの登場によって、映画とテレビの境界線がなくなってきました。またデジタル化によって表現の幅も広がっていると思います。 |
|---|---|
| 土井 | その意味ではテレビドラマのカメラマンもいろんなチャレンジができる時代。だからこそ「どういう画を撮りたい」「この物語はこういう画で表現したい」ということをもっと強く、表現者として持つことが大事なのかもしれません。たまに撮影開始の前に「土井さんはこういう世界観が好きだろう」と僕の過去作品のトーンなどから、嗜好を探ろうとしてくることがあって、それは作業や仕事の効率性などを考えてのことなんだろうけれど、特に若いカメラマンなどには、むしろ「自分なりのアプローチを見せてほしい」ってことを強く思いますね。 |