中継、音楽番組、
そしてドラマの世界へ

| ── | その後はしばらく中継一本ですか? |
|---|---|
| 星谷 | 僕の入った当時は中継班、バラエティー班、ドラマ班とカメラマンの専門領域が比較的分けられてはいたんですが、野球中継やった次の日はスタジオでの音楽番組やって、また別の中継やったりといくつかの現場を行き来するということもありました。その経験は実はすごく大きくて、いろいろな番組をやらせてもらいながらカメラマンとしての物の見方とかを育てられた気がしています。 |
| ── | 実際のところ、野球中継と音楽番組では何が違うのでしょうか? |
| 星谷 | 中継というのは決められたエリアがあって「ここから入っちゃいけません」という世界なんです。F1なんかが分かりやすいけれど、「この先に入ったらもっと迫力ある画が撮れるな」と思ってもガードレールより先には入ってはいけない。死んじゃいますから(笑)。決められたエリアの中でどれだけいい画が撮れるかを試行錯誤していく仕事です。もちろんそれはそれですごくやりがいがあるし面白いわけですけれど。一方で<MUSIC FAIR>や<夜のヒットスタジオ>といった音楽番組はその境界線がやや曖昧で、カメラマンの意志でもう少し中まで入っていける。極端にいうと他のカメラに写り込まない範囲だったら歌い手さんの横にがっつり近寄ってもいい。さらにドラマはカメラをどこに置く、どう撮るというのが演出の重要なポイントになってくるのである意味境界線がない。僕自身はいろんな番組をやる中で、そんなドラマの画づくりに徐々に魅力、やりがいを感じていくようになった。 |
| ── | 星谷さんをそうした方向に導いた憧れのカメラマンみたいな人はいるのですか? |
| 星谷 | 特定の誰かというわけではなく、多くの先輩の後ろ姿や撮った画を見てですよね。たとえばフジの代表作として多くのファンがいる<北の国から>というドラマ。後輩として憧れも抱いたし、そんなカメラマンの下でセカンドとしてついたときなど、本当に多くのことを学びましたからね。 |
| ── | 徒弟制度のように厳しく指導されるという感じですか? |
| 星谷 | いやむしろ「思い切って撮れ」と自由にさせてもらった感じです。実はドラマの場合、チーフカメラは決められた演出意図やカット割りに沿って確実に画を押さえなければいけないのに対して、セカンドカメラは冒険というか比較的自由がきく。だからそのセカンド時代にいろいろと工夫やチャレンジができた。「チーフカメラがああ撮るなら、自分はこうやってやろう」と。カメラマンとしてアピールできるポジションであり、自分の思いをストレートに試せるいい機会でした。 |
| ── | 星谷さんがチーフカメラマンになって担当した最初の作品は何だったんですか? |
|---|---|
| 星谷 | 1995年に公開された<花より男子>という映画でした。 |
| ── | 映画が初チーフ作品というのはすごいですね。 |
| 星谷 | 人から言われるとそんな気もしますが、当時は目の前の仕事に必死に取り組んでいたので、そこまで特別なことというふうには思っていなかったんです。もちろん、チーフとして現場を仕切らなくてはいけないという責任感と、レールひとつ敷くにも遠慮したりと、チーフデビュー作としての緊張感はやっぱりありましたけどね。大変だったけど、やってみたいと言い続けていたチーフカメラのポジション、やり遂げたときの達成感はひとしおでした。嫁さんと二人で映画館に観にいきましたよ。 |

| ── | いきなりの大役で、色んな意味で吸収するものがたくさんあったというわけですね。しかし、いきなり映画とは驚きです。ところで、放送の現場で「この番組には鍛えられたな」という機会はありましたか? |
|---|---|
| 星谷 | 思い出深いのはドラマではないのですが<なるほど! ザ・ワールド>ですね。番組の後半に「恋人選び」という名物コーナーがあって、本編が終わっての別撮りで出演者の解答にあわせて8人の顔が映ったパネルを順にパン※4したりズームしながら撮影するのですが、これが上手くいかない。なかなか決まらないなか、担当ディレクターが延々と付き合ってくれて何回も撮り直したってことがありました。今だったら「時間ないからもうこれでいい」で終わってしまうかもしれないけれど、当時は「パンが速いからもう一回!」、「ちょっとフレームが甘かったからもう一回!」と、それはしつこかった。今となってはこういう経験をさせてくれたディレクターには感謝しかありません。そして、そうした環境で恥をかくことで悔しくてたくさん練習したことは大きかったですね。 |
| ── | なるほど。たしかに恥をかいた経験って強く印象に残りますよね。では、ドラマではそうした経験がありましたか? |
| 星谷 | そうですね、恥とは少し違うのですが、ドラマでいうと<空から降る一億の星>という作品の雨のシーンかな。レールに乗ってカメラをパンするカットなんですが、何回やっても微妙なタイミングが合わず監督からのOKが出ない。その間ずっと主演の木村拓哉さんと明石家さんまさんがびしょ濡れで芝居しているわけです。申し訳ないという思いで何とか撮り終えたのですが、オンエア見たら結局そのカットが全然使われていないということがありましたね。 |



| ── | 何気なく見ているドラマのシーンの裏側で、作品作りに取り組むスタッフの想いや良い物を作り上げたいという姿勢が伝わってくるお話ですね。今、話に出たドラマ作品はいずれも中江功監督だと思いますが、<Dr.コトー診療所>も含めて星谷さんは中江さんと組まれることが多いですね。 |
|---|---|
| 星谷 | 最初に中江監督と組んだのは<翼をください!>でした。彼とは年齢は一緒なんですが入社年次は私の方が2つ上になるのかな。中江監督は独特の感性がある人なんです。なので、若い人の中には監督の言わんとしていることがなかなか伝わらず、悩んじゃうことがあるらしいんですが、僕の場合、「たぶんこういうことを言ってるんだろうな」と、長い付き合いから監督の欲しい画がなんとなく分かる。それを相性って言ってしまえばそれまでですが、そういう感性みたいなものが合うのかもしれないですね。 |
| ── | 逆にそうした感性が合わない場合の仕事は大変じゃないですか? |
| 星谷 | 僕はこう撮りたいと思っている、でも監督は違うってことはあります。ただ、そこで我を押し通せばいいのかといえばそうじゃない。おそらくカメラマンも演出家も「良い作品にしたい」って思いは同じで、そこへのアプローチで考え方が異なる。だからこそそうした時は徹底的に話し合いますね。その結果、監督が僕の意見を尊重してくれる時もあるし、僕が納得して監督の思い描く画を撮ることもある。意見が異なる場合こそキャッチボールが大切になってきます。 |

| ── | そうした中で星谷さんにとっての思い出の作品、思い出のシーンみたいものは? |
|---|---|
| 星谷 | やはり中江監督と組んでやった<Dr.コトー診療所>ですかね。あの作品は与那国島でロケを行って、島で長期間合宿のような生活をして撮りあげました。台風の影響でひたすら天気待ちしたり、でも待った甲斐があっただけの画が撮れたり。カメラマンとして納得もしたし、一方でたくさんの勉強をさせられた作品です。思い出のシーンというか、僕のカメラマン人生で忘れられない経験をしたのもこの作品でした。なんでもない夕日の中にポツンと自転車が置かれているだけのカットです。たまたま、その時は収録のビデオは回っていなかったんですよ。僕はただカメラを向けていただけ。自転車が醸し出す悲しげな雰囲気にウルっときました。で、後刻、同じカットをもう一回撮ろうとしたんですがその時の気持ちもあるのか、なぜか同じ感動が生まれない。その時に、ただ単純に物理的な配置とかだけで画の強さが生まれるんじゃなくて、光線とか空気とか時間とか、そんなものを含めて自分は撮っているんだな、ということを感じさせられました。ちょっとカッコつけていうと、僕の撮ったベストカットは僕しか見ていないってことですかね。 |

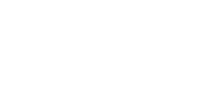


* 4 パン
カメラを左右方向に動かしながら撮影する操作のこと。